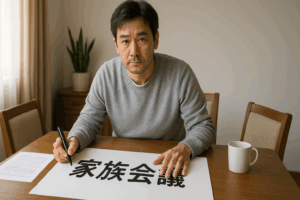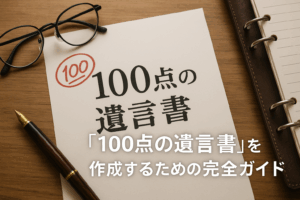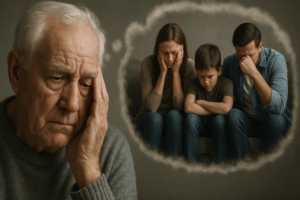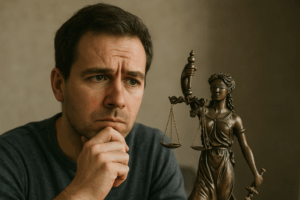「相続」という言葉には、財産を引き継ぐという事務的な響きとは裏腹に、時として人間の欲やエゴが生々しく現れる側面があります。中でも、近年問題視されているのが、特定の相続人が自身の利益を最大化するために、高齢で判断能力や身体能力が衰えた親を「囲い込み」、他の相続人から孤立させてしまうという、あまりにも身勝手な行為です。
「介護のため」「親のそばにいたいから」——。一見、親孝行にも見える言葉を隠れ蓑に、相続財産を独り占めしようと手段を選ばない相続人がいる現実。今回は、その恐るべき手口と、背景にある問題について警鐘を鳴らしたいと思います。
手口1:「介護同居」を盾にした情報遮断と洗脳
体が弱ってきた親を「私が面倒を見る」と宣言し、実家で同居を始める、あるいは自分の家に引き取る。これは、囲い込みの典型的な入り口です。最初は他の兄弟姉妹も「ありがたい」「任せるよ」と感謝するかもしれません。しかし、ここから巧妙な情報遮断と心理的な誘導が始まります。
- 物理的な接触の制限: 「親が疲れるから」「体調が悪いから」といった理由をつけて、他の兄弟姉妹や親戚が実家を訪問するのを拒んだり、電話を取り次がなかったりします。親の携帯電話を取り上げたり、かかってきた電話を勝手に切ったりすることも。
- 情報のコントロール: 親に届く郵便物を勝手に開封し、他の相続人に不利な情報や、逆に自分に都合の良い情報だけを親に伝えるようにします。
- 悪意ある吹き込み: 日常的に他の兄弟姉妹の悪口を吹き込み、「あの人はお金に汚い」「あなたのことなんて本当は心配していない」などと繰り返し伝えることで、親の不信感を煽り、自分だけが味方であるかのように思い込ませます。
このように、物理的にも精神的にも親を孤立させた上で、囲い込んでいる相続人は、自分に有利な状況を作り出そうとします。
囲い込みの目的:遺言書の書き換え、生前贈与、財産管理権の掌握
なぜ、そこまでして親を囲い込むのでしょうか。その目的は、多くの場合、相続における自身の取り分を最大化することにあります。
- 遺言書の作成・書き換えの強要: 親の判断能力が低下していることにつけ込み、「こう書くのが一番いい」「私が面倒を見るのだから、全財産を私に残すのが当然だ」などと言いくるめ、自分に有利な内容の遺言書を書かせようとします。時には、懇意にしている専門家を呼び、半ば強引に手続きを進めることもあります。
- 生前贈与の要求: 「介護費用がかかる」「家のリフォームが必要だ」など、様々な名目をつけて、親の預貯金や不動産などを生前に自分へ贈与させようとします。一度贈与されてしまえば、それはもはや遺産ではなく、囲い込んだ相続人の固有財産となります。
- 財産管理権の掌握: 親の預金通帳や印鑑、キャッシュカードなどを預かり、財産を自由に引き出せる状況を作ります。親の判断能力がさらに低下すれば、成年後見制度の利用をちらつかせ、自分が後見人候補者となることで、完全に財産をコントロールしようと図るケースもあります。
手口2:施設入所を悪用した「所在不明」化
同居による囲い込みが難しい場合、あるいはより巧妙に事を進めたい場合、介護施設への入所が悪用されることもあります。
- 独断での施設入所: 他の兄弟姉妹に相談なく、親を遠方の施設や、外部から連絡が取りにくい施設に入所させてしまいます。
- 「キーパーソン」としての情報独占: 施設への緊急連絡先や身元引受人(キーパーソン)を自分一人に限定し、「他の家族には連絡しないでほしい」「面会は私を通してほしい」などと施設側に伝え、情報を独占します。
- 居所の秘匿: 悪質なケースでは、他の兄弟姉妹に親が入所した施設の名前や場所すら教えず、連絡を取ることや面会すること自体を不可能にしてしまいます。「どこにいるか分からない」状態を作り出し、その間に遺言や贈与の手続きを進めようとするのです。
親の安全や適切なケアのためではなく、相続争いにおける「切り札」として施設入所が利用されるとしたら、それはあまりにも悲しい現実です。
囲い込みがもたらす悲劇
親の囲い込みは、囲い込んだ相続人以外の家族にとって、経済的な損失だけでなく、計り知れない精神的な苦痛をもたらします。
- 親との最後の時間を奪われる。
- 親の真意が分からないまま、相続手続きが進んでしまう。
- 長年築いてきた兄弟姉妹の関係が完全に破壊される。
そして何より、囲い込まれた親自身が、最も大きな被害者です。子供たちの争いに巻き込まれ、望まない孤立状態に置かれ、自分の意思とは異なる財産の処分を強いられる。晩節を汚され、尊厳を傷つけられることは、決してあってはならないことです。
私たちはどう向き合うべきか
「うちは大丈夫」と思っていても、親の高齢化や健康状態の変化、あるいは家族間の些細なすれ違いが、このような事態を引き起こす可能性はゼロではありません。
- 早期からのコミュニケーション: 親が元気なうちから、介護や相続について家族全員でオープンに話し合う機会を持つことが重要です。
- 定期的な連絡と訪問: 離れて暮らしていても、定期的に連絡を取り合い、可能であれば直接顔を合わせる機会を作りましょう。親の状況の変化や、特定の兄弟姉妹の不自然な言動に気づくきっかけになります。
- 情報の共有: 親の健康状態や介護の方針について、兄弟姉妹間で情報を共有し、誰か一人に情報が偏らないように意識することが大切です。
- 異変を感じたら: もし「囲い込みかもしれない」と感じる兆候(連絡が取れない、面会を拒否される、不自然な財産の動きなど)があれば、一人で悩まず、他の兄弟姉妹や親戚、場合によっては弁護士などの専門家に相談することも検討すべきです。成年後見制度の申し立てが必要になるケースもあります。
相続は、故人の遺志を尊重し、残された家族が円満に財産を引き継ぐためのプロセスであるはずです。それが、一部の相続人の私利私欲のために歪められ、親子の絆、兄弟の絆を断ち切る道具として使われることは、断じて許されるべきではありません。
何よりもまず、親自身の尊厳と幸福を第一に考える。その当たり前の倫理観を、相続に関わるすべての人が心に刻む必要があります。