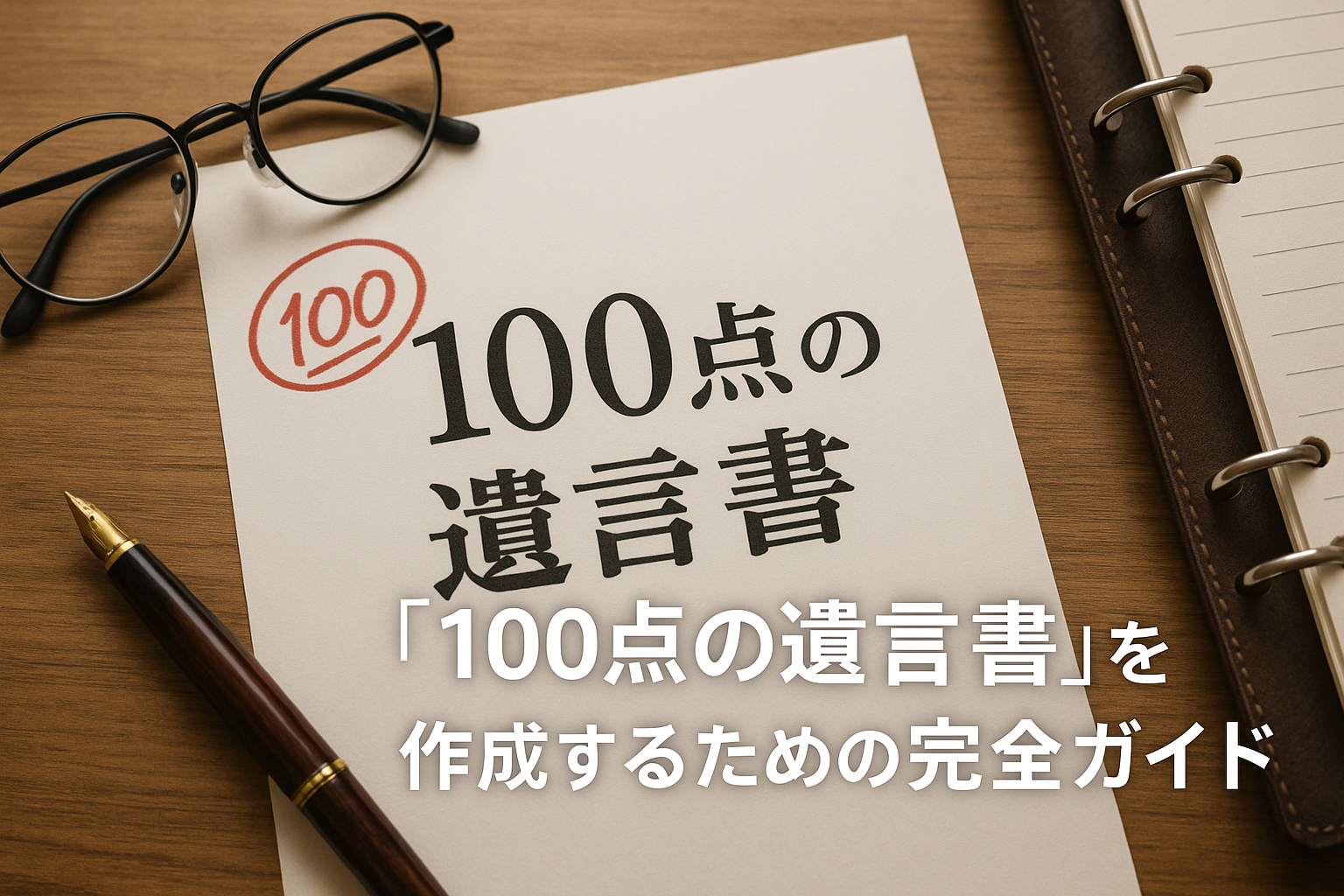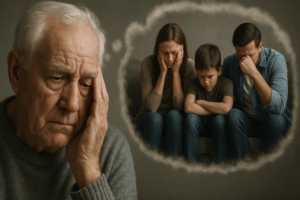遺言書は、ご自身の最後の想いを形にする大切なものです。「100点の遺言書」と一言で言っても、それはご家族への愛情や配慮が詰まった、法的に有効で、かつ円満な相続を実現できる遺言書と言えるでしょう。
この記事を読めば、
- 既に遺言の内容(誰がどの財産を取得するか)を決めている方は、その基準が本当に適切か、見落としがないかを確認できます。
- まだ内容が決まらないという方は、この記事で紹介する基準を参考に、ご自身にとって最適な遺言内容を具体的に決めていくことができます。
「100点の遺言書」作成は決して簡単ではありませんが、ポイントを押さえることで、より理想に近いものを作成することが可能です。この記事が、その一助となれば幸いです。
遺言書作成の9ステップ:後悔しないために押さえるべきこと
完璧な遺言書を作成するためには、段階を踏んで慎重に検討を進めることが重要です。ここでは、そのための具体的な9つのステップをご紹介します。
ステップ1:全ての財産について財産目録を作成する
まず、ご自身が所有する全ての財産をリストアップし、財産目録を作成しましょう。預貯金、不動産(土地・建物)、株式、投資信託、自動車、貴金属、美術品など、プラスの財産だけでなく、借入金やローンなどのマイナスの財産も正確に把握することが大切です。
そして、それぞれの財産について、以下のような特徴を把握してください。
- 誰が住んでいるか、利用しているか:自宅であれば同居家族、賃貸物件であれば入居者の状況など。
- 賃貸しているか:家賃収入の有無、契約内容など。
- どのぐらいの価値があるか:不動産であれば固定資産税評価額や市場価格、預貯金であれば現在の残高など。
可能であれば、相続税の試算も行っておきましょう。税理士に相談するのが確実ですが、ウェブサイトで簡易的に計算してみるのも一つの方法です。これにより、相続税がどの程度かかるのか、納税資金の準備が必要かなどを事前に把握できます。
ステップ2:家族関係のことを把握する
次に、ご自身の家族関係や、それぞれの状況を整理しましょう。
- 配偶者の状況:配偶者がいる場合、配偶者自身の財産がどの程度あるのかを考慮に入れることが大切です。老後の生活資金なども含めて考えましょう。
- 老後の世話:ご自身の老後の介護や生活の面倒を見てくれる人がいるか、あるいは期待する人がいるか。その人にどのように報いたいかを考える材料になります。
- 家族の考え方・生活状況:家族がどのような価値観や考え方をもっているか、また、それぞれのおおまかな財産状況や生活の状況を把握しておくと、遺産を分ける指針が立てやすくなります。
ステップ3:遺言内容の作成方針をたてる
財産と家族の状況を把握したら、いよいよ遺言内容の基本的な方針を立てます。遺産分けで何を最も重視するのか、どのようは基準を持つかを明確にしましょう。
- 法定相続分を基準にするか:民法で定められた相続割合を一つの目安とします。
- 相続税の節税を重視するか:二次相続(配偶者の相続)まで含めたトータルでの節税効果を考えるか。
- 各相続人への公平性を重視するか:金額的な公平性だけでなく、各相続人の状況に応じた配慮も大切です。
- 自分への貢献度を重視するか:生前の介護や事業への貢献などを評価するか。
- 遺留分を考慮するか:遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産の取り分)を侵害しないように分けるか、あえて侵害する内容にするか。
- 不動産の取り扱い:特定の不動産を誰かに残したいか、あるいは売却して金銭で分けても良いか。
- 祭祀財産(お墓や仏壇など)の承継者への配慮:お墓や納骨堂の管理・維持をしていく人に、その負担を考慮して多めに財産を分けるか。
- 生前贈与の考慮:既に特定の相続人に不動産や多額の金銭を生前贈与している場合は、その分を遺産分割で考慮する(特別受益として持ち戻す)ことで、他の相続人との公平性を保つことができます。
これらの方針を総合的に考えることで、ご自身の想いを反映した遺言の骨子が見えてきます。
ステップ4:各財産について、どのような分け方をすべきかを考える
作成方針が決まったら、個別の財産について具体的な分け方を検討します。
その中で、下記の財産については、特別な配慮が必要となります。
- 居住用不動産:相続人の誰かが現在住んでいる不動産は、原則としてその居住者に相続させるのがスムーズです。
- 自社株式:会社を経営している場合、その株式は事業を継ぐ方に相続させるのが一般的です。
- 賃貸物件(ローン付き):相続税対策などでローンを組んで購入した賃貸物件は、賃貸経営を引き継ぐ人に不動産とローンをセットで相続させるのが合理的です。将来的に高額な修繕費がかかる可能性も考慮し、修繕費に充当できる程度の預貯金も合わせて残すことを検討しましょう。
ステップ5:相続税の支払いが問題ないかを確認する
決定した遺産の分け方で、各相続人がどの程度の相続税を支払うことになるのかを再度確認します。
- 納税資金の確保:不動産など換金性の低い財産のみを相続した人は、相続税の支払いに困窮し、結局その不動産を売却せざるを得なくなるケースがあります。
- 預貯金での準備:相続税に充てる金額は、できる限り預貯金で残し、相続した預貯金で相続税を支払えるようにするのが原則です。
相続税の支払いまで考慮して、必要であれば財産の分け方を修正しましょう。
ステップ6:遺留分について、問題ないか考える
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。
- 遺留分権利者の確認と侵害の有無:作成した遺言内容が、遺留分権利者の遺留分を侵害していないかを確認します。
- 侵害している場合の対応:
- 修正する:遺留分を侵害しないように、財産の分け方を変更します。
- 無視する(あえて侵害する):特定の相続人に多くの財産を残したいなどの理由で、あえて遺留分を侵害する内容にする場合は、そのリスクを理解しておく必要があります。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行う権利があります。
- 遺留分を無視する場合の対策:遺留分侵害額請求をされることを見越して、請求される可能性のある相続人に対して、遺留分相当額の金銭を別途遺贈するなどの対策を検討することも考えられます。
ステップ7:相続財産をもらう方が自分より先に亡くなっていた場合のことを考える
遺言書を作成しても、相続財産を受け取る予定だった人が、ご自身より先に亡くなってしまう可能性はゼロではありません。特に配偶者は同年代であることが多く、また、人生100年時代においては、子供が先に亡くなるということもあり得ます。
- 予備的遺言の検討:このような事態に備えて、「もし〇〇(相続人)が自分より先に死亡した場合は、その財産は△△(次の相続人候補)に相続させる」といった形で、予備的な受取人を指定しておく(予備的遺言)ことを検討しましょう。これにより、意図しない人に財産が渡ることを防ぎ、ご自身の意思をより確実に実現できます。
ステップ8:祭祀主催者の指定について考えます
お墓、納骨堂、位牌、仏壇などの財産を「祭祀財産」といいます。これらは、通常の相続財産とは区別され、相続とは異なる形で承継者が決まります。
- 祭祀財産の特殊性:誰がお墓や仏壇を引き継ぎ、管理・供養していくかは、費用負担も伴うため、相続人間で揉める原因になることがあります。
- 祭祀主催者の指定:このようなトラブルを避けるため、遺言書で祭祀財産を取得し、祖先の祭祀を主宰する「祭祀主催者」を指定することができます。誰に任せるのが適切か、その人の負担も考慮して慎重に決めましょう。
ステップ9:付言を考える
付言(ふげん)とは、遺言書の最後に添えるメッセージのことです。法的な効力はありませんが、ご自身の想いを相続人に伝えるための重要な手段となります。
- 付言の役割:遺言書による財産分与は、必ずしも全ての相続人にとって完全に公平とはならない場合があります。そのため、中には不満を抱く相続人が出てくる可能性も否定できません。
- 紛争予防効果:不満が大きくなると、遺留分侵害額請求などで紛争に発展することもあります。遺言の内容が円満に実現するためには、特に財産が少なかったり、もらえなかったりする相続人への精神的なフォローが重要です。
- 理由を伝える大切さ:付言に、なぜそのような遺産分割にしたのか、その理由や各相続人への感謝の気持ちなどを具体的に書き記すことで、相続人の理解を得やすくなります。逆に、理由が書かれていないと、「自分は愛されていなかった」「自分のことを理解してもらえなかった」といった悲しみから、相続争いに発展してしまうことも少なくありません。
まとめ:専門家の力も借りて「100点の遺言書」を目指しましょう
以上が、遺言の内容を決定するための一般的な方法と、その際の重要な考慮点です。しかし、これらはあくまで一般的な指針であり、個々のケースによっては、他にも検討すべき事項が出てくることもあります。
ご自身の頭の中だけで、これら全てのことを整理し、客観的に見て問題のない遺言書を作成するのは、非常に難しい作業です。財産の評価、相続税の試算、遺留分の計算など、専門的な知識がなければ正確に行えない部分も多く含まれます。
「100点の遺言書」は、ご自身の想いを実現し、残されたご家族が円満に相続手続きを進められるようにするためのものです。そのためには、専門家の関与のもとで作成することを強くおすすめします。 専門家は、法的な観点だけでなく、税務面や感情面にも配慮したアドバイスをしてくれるでしょう。
この記事が、皆様の「100点の遺言書」作成の一助となれば幸いです。