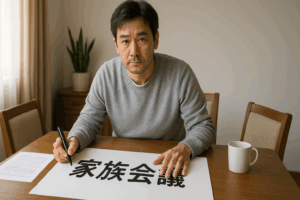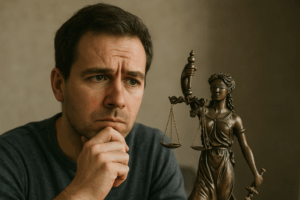相続が開始すると、「びた一文、1円たりとも渡さない!」と強く主張する人が現れることがあります。このような状況は、他の相続人にとって大きな精神的負担となり、遺産分割協議を暗礁に乗り上げさせます。
本コラムでは、遺産分割が難しくなるパターンの一つである、「法定相続分」を受け入れられない相続人に対し、どのように対処すべきか、相続人の心情を読み解き、それにより導かれる解決方法について解説します。
「1円もやらない」という主張の裏にある心理と価値観
この強い拒絶の背景には、単なる欲深さだけではない、複雑な感情や長年の思い、独自の価値観が隠されていることが少なくありません。
- 「自分が親の面倒を一番見てきた」という自負と不公平感: 長年にわたり献身的に親の介護をしてきた、あるいは経済的に支えてきた相続人は、「他の兄弟姉妹は何もしてこなかったのに、同じように遺産をもらうのはおかしい」と感じることがあります。その労苦が報われていない、正当に評価されていないという強い不満が、「1円も渡したくない」という感情につながるのです。彼らにとっては、遺産の分配が、自身の貢献度や故人への愛情を測るバロメーターのように感じられるのかもしれません。
- 故人との確執: 生前、故人と相続人の一人との間に確執があり、故人の財産を渡したくないとの言葉を聞いていた等の事情で、「あの人にだけは、遺産を渡したくない」という感情が生じていることがあります。過去の家族間の出来事が、現在の相続問題に影を落としているケースです。
- 「家」や「財産」に対する強い思い入れ: 特定の不動産(実家など)や事業を両親に託されており、「これは自分が守るべきものだ」「他の者には渡せない」という強い執着心を持つ相続人もいます。それは、単なる資産価値を超えた、自身のアイデンティティや家族の歴史と結びついた特別な価値観に基づいている場合があります。
- 経済的な困窮や将来への不安: 自身の経済状況に余裕がなく、相続財産を生活の支えにしなければならない、あるいは将来への強い不安を抱えている場合、少しでも多くの遺産を確保したいという思いが「1円も渡さない」という強硬な姿勢につながることもあります。
- 誤解や情報不足: 相続に関する法律や制度(法定相続分や遺留分など)について正確な知識がなく、「長男だから全て相続できるはずだ」「故人が口頭でそう言っていた」といった誤解に基づいて主張している可能性も考えられます。
頑なな相続人への対応ステップ
感情的になっている相手に、いきなり法律論をぶつけたり、感情的に反論したりしても、事態は好転しません。むしろ、より意固地にならせてしまう可能性があります。冷静かつ段階的に対応することが重要です。
- まずは「聴く」姿勢を大切に: なぜ「1円もやらない」と主張するのか、その理由や背景にある感情を、まずは冷静に、遮らずに最後まで聴きましょう。相手の言い分を全て受け入れる必要はありませんが、「あなたがそう考える背景には、こういう思いがあるのですね」と、一定の理解を示す(共感ではなく、理解の表明)ことで、相手の警戒心を解き、対話の糸口が見つかることがあります。
- 感情と事実を切り分ける: 相手の主張が感情的なものなのか、それとも何らかの事実誤認に基づいているのかを見極めます。感情的な部分には寄り添いつつも、法律上の権利や客観的な事実については、冷静に、わかりやすく伝える努力が必要です。
- 法律上のルール(法定相続分・遺留分)を伝える: 相続には法律で定められたルールがあることを、穏やかに説明します。「法律では、配偶者や子にはこれだけの割合(法定相続分)が保障されていること」「たとえ遺言で特定の相続人に全てを遺すと書かれていても、他の相続人には最低限の取り分(遺留分)を請求する権利があること」などを、資料(簡単な図やパンフレットなど)を交えながら説明すると、理解を得やすくなる場合があります。
- 第三者の専門家への相談を提案する: 当事者同士では感情的な対立が解けない場合、公平な第三者である専門家(弁護士や司法書士など)に相談することを提案してみましょう。「お互いの言い分を整理し、法律に則った円満な解決策を一緒に探してもらいませんか?」という形で提案すれば、相手も受け入れやすくなるかもしれません。最初から敵対的に弁護士を立てるのではなく、まずは「相談」という形でハードルを下げることがポイントです。
どうしても話し合いが進まない場合
上記の対応を試みても、相手の態度が軟化せず、遺産分割協議が全く進まない場合は、法的な手続きを検討せざるを得ません。
- 弁護士への依頼: 各相続人がそれぞれ弁護士に依頼し、代理人を通じて交渉を進めます。直接顔を合わせずに済むため、感情的なぶつかり合いを避けられます。弁護士は法律に基づき、依頼者の権利を主張し、相手方と交渉を行います。
- 家庭裁判所への遺産分割調停の申立て: それでも合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停は、裁判官と民間の調停委員が間に入り、相続人双方の言い分を聴きながら、話し合いによる合意を目指す手続きです。あくまで話し合いが基本ですが、第三者が関与することで、冷静な議論が進みやすくなります。
- 遺産分割審判: 調停でも合意できなかった場合は、自動的に審判手続きに移行します。審判では、裁判官が、提出された資料や各相続人の主張、法律などを総合的に考慮し、遺産の分割方法を決定します。これは裁判所の決定であり、強制力を持ちます。
まとめ:焦らず、諦めず、着実な解決を目指して
「1円もやらない!」という相続人の頑なな態度は、多くの場合、複雑な感情や背景が絡み合っています。まずはその心情に一定の理解を示し、冷静な対話を試みることが第一歩です。しかし、感情論だけでは解決できないのが相続問題の難しさでもあります。
法律という客観的なルールを適切に伝え、必要であれば弁護士などの専門家の力を借り、最終的には家庭裁判所の手続きも視野に入れながら、焦らず、しかし諦めずに、着実な解決を目指していくことが重要です。相続争いは、故人が望んだことではないはずです。可能な限り円満な解決を図り、故人を安らかに見送ることが、残された者の務めと言えるでしょう。