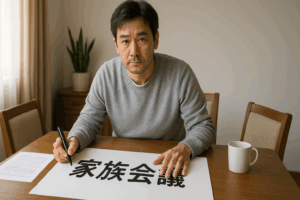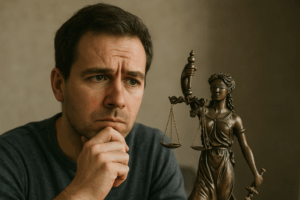ある日突然、弁護士事務所から相続に関する通知が届いたら…? 驚きと不安でいっぱいになるかもしれません。
しかし、焦る必要はありません。今回は、弁護士から相続に関する通知が届いたときに、冷静に対応するための大切なポイントを7つご紹介します。
とにかく、焦らず、専門家への相談に行く。期限を切られても、気にする必要はないということが最大のポイントです。
1. まずは深呼吸! 焦らないことが何よりも大切
弁護士からの封筒、物々しい書面の雰囲気に、まず「どうしよう!」とパニックになってしまうかもしれません。しかし、**一番大切なのは『焦らないこと』**です。
通知には「〇日以内にご回答ください」「〇月〇日までにご連絡を」といった期限が書かれていることがあります。しかし、これは多くの場合、相手方の弁護士が独自に設定した期限であり、法的な強制力を持つものではありません。もちろん、無視して良いわけではありませんが、「その日までに返事をしないと大変なことになる!」と過度に思い詰める必要はないのです。
もし、すぐに回答できない場合や、内容を検討するのに時間が必要な場合は、「内容を確認し、検討するため、回答には少しお時間をください」とその旨だけを正直に連絡すれば問題ありません。
2. 相手方の弁護士は「あなたの味方」ではない
次に理解すべき重要な点は、通知を送ってきた弁護士は**『相手方の代理人』**であるということです。彼らは依頼者(あなたにとっての他の相続人など)の利益を最大化するために動いています。
そのため、通知に書かれている内容や主張は、当然ながら相手方の意向を反映したものです。
弁護士を公平な立場で、法的に正しいことを言っているという勘違いをしてしまうと、弁護士の発言をうのみにし、こちらの主張が十分にできず、あきらめてしまうという方がいます。
もし、あなたが正しい主張をしたとしても、基本的に否定的な立場をとってくると考えた方が良いでしょう。弁護士という専門家からの通知だからといって、全面的に受け入れる必要はありませんし、こちらの主張に対し、否定的な返答があったとしても、当然のことですので、「弁護士に歯向かったら、損をするのではないか。負けるのではないか。」と弱気になる必要はありません。
3. 弁護士の主張=法的に絶対正しい、ではない
「弁護士が言っているのだから、法的に正しいのだろう…」そう考えてしまうかもしれません。しかし、弁護士からの通知に書かれている内容が、すべて法的に正しい、あるいは唯一の解決策とは限りません。
あくまで相手方の「希望」や「主張」が述べられているに過ぎない場合も多いのです。もし、相手方の主張に疑問がある場合や、ご自身の正当な権利があると感じる場合は、臆することなく、ご自身の主張をする準備をしましょう。 諦める必要はまったくありません。
4. 弁護士介入後の直接交渉は原則NG
相手方に弁護士がついた場合、相続に関して相手方本人と直接の話し合いは避けるのが基本的なルールです。これは、弁護士の主張と相手方本人との主張に食い違いがでて、どちらの主張が正しいのか分からなくなったり、感情的な言い争いになったり、言った言わないの水掛け論になったりするなど、かえってトラブルを大きくしてしまう可能性があるためです。今後は、相手方の弁護士を通じてやり取りをするのが基本となります。
ただし、法事の日程調整や、相続とは直接関係のない事務連絡などについては、常識の範囲内で直接やり取りしても問題ない場合が多いです。
5. 通知の内容は様々。すぐに裁判ではない場合も多い
弁護士からの通知には、いくつかの種類があります。
- 受任通知: 単に「依頼を受け、代理人として遺産分割協議を開始したい」という意思表示だけのもの。具体的な要求はなく、まずは話し合いのテーブルにつきましょう、という段階です。
- 具体的な遺産分割案の提示: 相手方が希望する遺産分割の方法が具体的に書かれているもの。
たとえ具体的な分割案が書かれていて、それに同意できない場合でも、「同意しなければ即、裁判所の調停や審判になる」というわけではありません。そのように書かれていたとしても、それは相手方のプレッシャーである可能性もあります。多くの場合、交渉の余地は残されています。なぜなら、遺産分割は相続人全員の合意がなければ進まないことを、相手方も弁護士も理解しているからです。
6. 「法定相続分」が基本ラインになることを知っておく
もし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判に進むことになりますが、その場合、原則として**『法定相続分』**に基づいて遺産が分割されることが多くなります。法定相続分とは、民法で定められた各相続人の取り分の割合のことです。
この「法定相続分」を一つの基準として知っておくことは、相手方との交渉を進める上で、ご自身の主張を組み立てる参考になります。
7. 一人で悩まず、専門家への相談と比較検討を
弁護士から通知が来た段階で、速やかにご自身も専門家(弁護士や相続に詳しい司法書士など)に相談することを強くお勧めします。
通知の内容を正確に理解し、法的な観点からご自身の状況や権利を把握することが重要です。そして、今後の対応方針についてアドバイスを受け、必要であればご自身も弁護士に代理人を依頼することを検討しましょう。相手に弁護士がついている以上、こちらも専門家を立てることで、対等な立場で交渉を進めることができます。
また、可能であれば、他の相続人と連絡を取り、状況を共有したり、対応方針について話し合ったりすることも有効です。利害が一致する相続人がいれば、足並みをそろえることで、交渉を有利に進められる場合があります。
まとめ
弁護士からの相続に関する通知は、確かに驚く出来事ですが、決してパニックになる必要はありません。
- 焦らない
- 相手の弁護士は相手の味方と認識する
- 相手の主張が絶対ではないと知る
- 直接交渉は避ける
- すぐに裁判ではない場合が多いと理解する
- 法定相続分を意識する
- 専門家に相談し、こちらも弁護士依頼を検討する。他の相続人との連携も視野に。
これらのポイントを念頭に、冷静に状況を把握し、相手方の主張を鵜呑みにせず、専門家のアドバイスを求め、ご自身の権利を守るために適切な行動をとることが重要です。一人で抱え込まず、早めに信頼できる専門家を見つけて相談してくださいね。