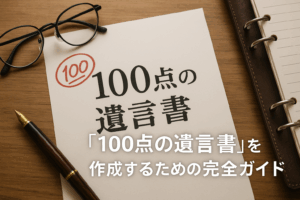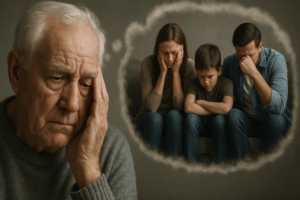「家族じまい」という言葉を聞いたことがありますか?近年、耳にする機会が増えたこの言葉は、法的な手続きによるものではなく、家族間の関係性を主に子供が断ち切ることを言います。この記事では、なぜ「家族じまい」が起こるのか、その原因を探り、どうすれば避けられるのか、その知恵について考えていきます。
この記事を読むことで、誰にでも起こりうる、家族関係の崩壊の事実とその原因、そして、そうならないための対処法を知ることができます。
特に親御さんが高齢期を迎える、あるいは迎えている方にとっては、より良い関係を築き、後悔しないための大切な視点が見つかるはずです。
「家族じまい」という言葉を知っていますか?
「家族じまい」とは、親子や兄弟姉妹といった家族の関係を実質的に断絶することを意味する新しい言葉です。
日本の法律では、親子や兄弟姉妹といった関係を法的に「切る」ことは、養子縁組の解消などを除き、基本的にはできません。戸籍上の繋がりは、本人の意思だけでは消せないのです。
しかし、法律上の繋がりはあっても、それとは関係なく、高齢の両親のお世話の拒否や身元保証の拒否等からはじまり、ついには「絶縁状態」や「疎遠」になり、何年も、あるいは生涯にわたって交流が途絶えてしまう家族は少なくありません。
なぜ「家族じまい」は起こるのか?関係が壊れる原因
特に親が高齢になると、介護が必要になったり、判断能力が低下したりする中で、様々な要因が絡み合い、関係が崩壊へと向かうことがあります。
関係が壊れる主な原因を見ていきましょう。
- 老後の世話(介護)の困難さ:
- 介護は精神的・肉体的・経済的に大きな負担となります。終わりが見えない介護生活に、世話をする側の子供が疲弊してしまうケースは少なくありません。
- 老後の親子関係の複雑さ:
- 親が老い、子供が親の面倒を見るようになると、それまでの「親が上で子が下」という関係性が逆転します。この変化に親も子も戸惑い、精神的な摩擦が生じやすくなります。「いつまでも親はしっかりしている」と思っていた子供、「子供に頼りたくない」と思っていた親、双方の思いがすれ違うことがあります。
- 「してあげた」という恩着せがましさ:
- 親が子に「これだけしてあげたのに」、あるいは子が親に「こんなにしてあげているのに」という気持ちが強くなると、関係は歪み始めます。見返りを期待する気持ちや、感謝されないことへの不満が、溝を深める原因になります。
- 子供世代の生活の余裕のなさ:
- 子供世代も、自身の仕事、子育て、住宅ローンなど、様々なプレッシャーの中で生活しています。親の世話まで手が回らない、経済的・時間的な余裕がないという現実も、関係悪化の一因です。そして、それに対して親が配慮しないことも問題を大きくします。
- 認知症・脳の機能低下:
- 親の認知症や脳機能の低下は、コミュニケーションを困難にし、家族を混乱させます。物忘れ、性格の変化、被害妄想などに対し、どう対応していいかわからず、子供が精神的に追い詰められることがあります。
- 子供世代の知識不足:
- 認知症や高齢期の心身の変化について、子供世代が十分な知識を持っていないことも問題です。病気の症状を「わがまま」「嫌がらせ」と捉えてしまい、関係が悪化するケースが見られます。また、介護保険サービスや地域包括支援センターなどの社会資源についての知識がないために、一人で抱え込んでしまうこともあります。
- 世話をする子・しない子の間の格差と不公平感:
- 複数の子供がいる場合、主に親の近くに住む子供や特定の子供(例えば長男・長女など)が介護負担を多く背負う傾向があります。
- 世話をする子の葛藤: 一生懸命世話をしても、親からは「あれが足りない」「これが不満だ」と要求されがちです。一方で、たまにしか顔を見せない他の兄弟姉妹は、親から歓迎され、良い顔をされることがあります。世話をする子は「自分の苦労は報われない」と感じやすくなります。
- 相続での不公平感: 献身的に介護をしても、遺産相続では他の兄弟姉妹と同じ扱い、あるいはほとんど配慮されないケースも多く、「骨折り損のくたびれ儲け」とまではいわなくとも、あまりの不公平感に心にモヤモヤを感じてしまいます。
- 世話をしない子の不信感: 介護に関わらない兄弟姉妹は、実際に介護をしている兄弟姉妹の苦労を理解しにくいものです。それどころか、「親の財産を使い込んでいるのではないか」「親からお金をもらっているのではないか」と疑いの目を向けることさえあります。
- 複数の子供がいる場合、主に親の近くに住む子供や特定の子供(例えば長男・長女など)が介護負担を多く背負う傾向があります。
- 在宅介護への固執と施設への偏見:
- 「家で最期まで過ごしたい」と強く願う親や、「親を施設に入れるのは姥捨て山だ」「人生の墓場だ」という誤ったイメージや考え方を持つ家族(親自身や、介護に関わらない子供など)がいると、在宅介護が限界に達していても、他の選択肢を選びづらくなります。これが介護者を追い詰める一因となります。
関係を壊さないために、今からできること(対策)
「家族じまい」は決して他人事ではありません。しかし、原因を知り、早めに対策を講じることで、そのリスクを減らすことは可能です。
- 親子で「老い」について学ぶ:
- 人は誰でも老います。高齢になると心身にどのような変化が起こるのか、認知症とはどのような病気なのか、親子双方がある程度の知識を持つことが大切です。自治体の講座や書籍、信頼できるウェブサイトなどを活用しましょう。
- 互いを思いやる心を持つ:
- 親子であっても、別の人間です。価値観の違いは当然あります。親は「子供にも生活がある」ことを理解し、子は「親の心身の衰えによる自信喪失や孤独を抱えていること」を理解し、お互いを思いやる気持ちを持つことが基本です。感謝の気持ちを言葉で伝えることも大切です。
- 世話をする家族への感謝とリスペクト:
- 両親のお世話や介護を主に担ってくれる兄弟姉妹がいる場合、他の家族はその負担と貢献に心からの感謝と敬意を示しましょう。具体的な協力(金銭的援助、一時的な介護の交代、話し相手になるなど)を申し出ることも重要です。「ありがとう」の一言が、関係を良好に保つ潤滑油になります。
- 高齢化・認知症への備え(元気なうちから):
- 財産管理: 親の判断能力がしっかりしているうちに、預貯金や不動産の管理について話し合い、必要であれば信頼できる子供に任せる(財産管理委任契約)、あるいは将来のために任意後見制度の利用を検討しましょう。
- 介護方針: もし介護が必要になったら、どこで(自宅か、施設か)、誰が中心になって、どのように介護を受けたいか、親の意向を確認し、家族で話し合っておきましょう。エンディングノートなどを活用するのも良い方法です。
- 相続対策(元気なうちから):
- 親の世話(特に介護)を献身的に行った子供が、相続において不利益を被らないように、親が元気なうちに話し合い、対策を講じておくことが望ましいです。
- 遺言書: 親の意思として、介護の貢献度を考慮した遺産の分割方法を記しておく。
- 生前贈与: 感謝の気持ちとして、介護をしてくれる子供に生前に財産を贈与する。
- 寄与分: 相続発生後、他の相続人に「寄与分」を主張することも可能ですが、相続人間の話でも、もし、裁判所での調停、審判となっても認められるハードルは高いのが現状です。できるだけ遺言書や生前贈与での対策しておくことが、争いを避ける道です。
- 相続については、専門家への相談も有効です。
- 親の世話(特に介護)を献身的に行った子供が、相続において不利益を被らないように、親が元気なうちに話し合い、対策を講じておくことが望ましいです。
まとめ
「家族じまい」は、様々な要因が複雑に絡み合って起こります。特に、親の高齢化に伴う介護や相続の問題は、家族関係に大きな影響を与えがちです。
しかし、問題が起こる前に、あるいは起こり始めた段階で、家族が互いを尊重し、オープンに話し合い、必要な知識を身につけ、早めに備えることで、関係の破綻を防ぐことは十分に可能です。
この記事が、皆さんの大切な家族との関係を、より良いものにしていくための一助となれば幸いです。まずは、ご家族と「これから」について話す時間を持ってみてはいかがでしょうか。
当社では、両親の高齢化・認知症対策と相続対策に取り組んでおります。ぜひ、ご相談いただけたらと思います。