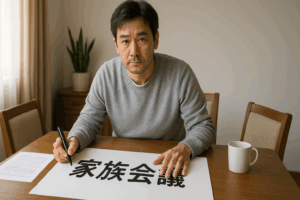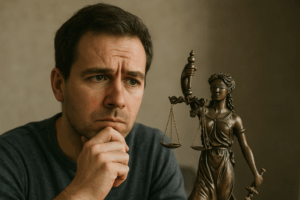「まさか、自分の身にこんなドラマみたいなことが起こるなんて…」
相続を経験された方の中には、そう呟きたくなるような現実に直面した方もいらっしゃいます。遺産相続は、時として人生を大きく、そして必ずしも良い方向ではない方へと変えてしまう力を持っています。財産を引き継ぐという側面だけでなく、それまで築き上げてきた家族関係をも根底から揺るがしかねない、非常にデリケートな問題なのです。
今回は、相続をきっかけに起こりがちな悲劇的なケースと、それを避けるため、あるいは解決するための方法について考えていきましょう。
ケース1:昨日までの「仲良し家族」が、相続で「争続」へ
「うちは家族仲が良いから大丈夫」——そう思っていた家族が、相続をきっかけに関係に深い亀裂が入ってしまうケースは後を絶ちません。
例えば、両親が亡くなり、実家と預貯金を子供たちで分けることになったとします。長男は「自分が家を継ぐのが当然」、次男は「公平に分割してほしい」、長女は「生前、親の介護を一番頑張ったのは私だから、多くもらう権利があるはず」…など、それぞれの立場や想い、そして「期待」がぶつかり合います。
最初は冷静に話し合おうとしても、不動産の評価額、預貯金の分け方、形見分けの品の価値など、具体的な話になるにつれて感情的になりがちです。「昔からお兄ちゃんは優遇されていた」「あなたは何もしてくれなかった」といった過去の不満まで噴出し、収拾がつかなくなることも少なくありません。
お金の問題だけでなく、親の想いや、きょうだい間の公平感といった感情的な要素が絡み合い、一度こじれると修復は困難を極めます。「争う相続」と書いて「争続」と揶揶揄されるように、骨肉の争いは、弁護士を立てての調停や裁判に発展し、家族は完全にバラバラになってしまうのです。
ケース2:子供のいない夫婦、夫の死後、妻に告げられた「家を出ていけ」
子供のいない夫婦の場合、夫が亡くなった際の相続関係は少し複雑になります。夫の両親がすでに他界している場合、法定相続人は妻と夫の兄弟姉妹(甥姪も含む場合あり)になります。
長年連れ添った夫が亡くなり、悲しみに暮れる妻。夫と二人で築き上げてきた自宅で、思い出と共にこれからも暮らしていきたいと願っていました。しかし、ある日、夫の兄弟たちが現れ、こう告げるのです。「この家は我々にも相続権がある。家を売却して遺産を分けたいから、出ていってほしい」と。
法律上、夫の兄弟姉妹にも相続分(このケースでは、妻が3/4、兄弟姉妹が合わせて1/4)が認められています。もし主な遺産が自宅不動産のみだった場合、妻が住み続けるためには、兄弟姉妹の相続分に相当する現金を代償金として支払う(代償分割)か、家を共有名義にするなどの方法がありますが、現金がなければ支払えませんし、共有名義は将来的なトラブルの種になりかねません。
長年住み慣れた家を追い出されるかもしれないという不安、そして何より、夫の死後にその兄弟たちからこのような要求をされる精神的な苦痛は計り知れません。生前の夫は、まさか自分の兄弟が妻にそんなことを言うとは夢にも思っていなかったでしょう。
ケース3:「介護を頑張ったのに…」寄与分をめぐる対立
被相続人(亡くなった方)の生前に、特定の相続人が療養看護や財産の維持・増加に特別な貢献をした場合、その貢献分を相続財産に加味する「寄与分」という制度があります。しかし、この寄与分が新たな火種となることも少なくありません。
例えば、長女が仕事を辞めて実家に戻り、何年もの間、寝たきりの母親の介護を一身に引き受けていたとします。他の兄弟は週末に顔を見せる程度でした。母親が亡くなり遺産分割協議になった際、長女は「自分の貢献(寄与分)を考慮して、他の兄弟よりも多く遺産をもらうべきだ」と主張しました。
しかし、他の兄弟は「親の介護をするのは当たり前だ」「そこまで特別な貢献とは言えない」「そもそも寄与分を具体的にどう評価するのか」と反論。感情的なしこりも相まって、話し合いは平行線をたどります。
寄与分は、法的に認められるためのハードルが意外に高く、認められたとしてもその評価額を巡って争いになることが非常に多いのです。「頑張りが報われない」という介護者の無念さと、他の相続人の不公平感がぶつかり合い、家族関係に深い溝を作ってしまいます。
ケース4:突然発覚した多額の借金! 相続すべきか、放棄すべきか…
相続は、プラスの財産(不動産、預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、保証債務など)も引き継ぐものです。亡くなった方に多額の借金があることを、相続が始まってから初めて知るケースも珍しくありません。
父親が亡くなり、相続人である子供たちが遺産を調査し始めたところ、消費者金融からの多額の借り入れや、知人の事業の連帯保証人になっていることが発覚しました。預貯金やわずかな不動産を合わせても、到底借金を返済できる額ではありません。
この場合、相続人は「単純承認」(すべての財産と借金を相続する)、「相続放棄」(すべての財産と借金の相続権を放棄する)、「限定承認」(プラスの財産の範囲内で借金を返済し、残れば相続する)のいずれかを選択しなければなりません。
相続放棄や限定承認は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。突然の借金発覚に動揺し、この期間を過ぎてしまうと、原則として単純承認したとみなされ、被相続人の借金をすべて背負うことになりかねません。知らなかった借金のために、相続人の人生設計が大きく狂ってしまう悲劇です。
ケース5:不動産はあるのに現金がない! 払えない相続税
遺産の大部分が不動産で、相続税の納税資金となる現金や預貯金が少ない場合も、深刻な問題を引き起こします。
例えば、都心の一等地に長年住んでいた両親が亡くなり、子供たちが実家を相続することになったとします。子供たちは、思い出の詰まった実家を売却したくないと考えていました。しかし、土地の評価額が高いため、相続税も高額になることが判明。ところが、両親が残した預貯金は少なく、相続税を支払うには全く足りません。
相続税は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、現金で一括納付しなければなりません。納税資金がなければ、相続人たちは以下のような厳しい選択を迫られます。
- 不動産の売却: 結局、思い出の家や土地を手放さざるを得なくなる。期限が迫る中での売却は、買い叩かれるリスクもあります。
- 借金: 相続人が金融機関などから個人的に借金をして納税する。相続した財産以上に、将来にわたる返済負担を負うことになります。
- 延納・物納: 一定の要件を満たせば、税金の分割払い(延納)や不動産そのもので税金を納める(物納)も可能ですが、手続きは複雑で、必ず認められるわけではありません。
結局、このケースでは、兄弟のうち一人が代表して銀行から多額のローンを組んで相続税を支払い、他の兄弟はその相続分に応じて、長期にわたり返済していくことになりました。納税はできましたが、予期せぬ借金は相続人たちの生活に重くのしかかり、なぜ生前に納税資金の準備をしてくれなかったのかという、故人への複雑な感情や、相続人間の負担の不公平感を残す結果となりました。
悲劇を回避・解決するためにできること
このような「争続」や悲劇を避けるためには、どうすれば良いのでしょうか。
- 生前の対策:遺言書の作成 最も有効な対策の一つが、「遺言書」を作成しておくことです。法定相続分とは異なる分け方をしたい場合(例:介護の貢献に報いたい、特定の相続人に自宅を残したい)や、相続人以外の人(内縁の妻など)に財産を残したい場合に特に有効です。遺言で相続分や分割方法を指定することで、争いを予防できます。 公正証書遺言など、法的に有効で、かつ内容が明確な遺言書を作成しておくことが重要です。
- 生前の対策:財産状況の整理と納税資金の準備 自身の財産(プラス・マイナス両方)を把握し、リスト化しておくことが大切です。特に不動産など評価額が高い財産がある場合は、おおよその相続税額を試算し、納税資金をどう準備するか(生命保険の活用、生前贈与、資産の組み換え等)を検討しておくべきです。エンディングノートなども活用しましょう。
- 生前の話し合い:家族会議 遺言書がない場合でも、生前に家族で相続について話し合っておくことは、無用な争いを避ける助けになります。財産状況、親の想い、各相続人の希望、貢献度などをオープンに話し合い、認識を共有しておくことが重要です。
- 相続開始後の迅速な調査と対応 相続が開始したら、速やかに被相続人の財産(プラス・マイナス両方)を正確に把握しましょう。借金の有無、不動産の評価額などを調査し、相続税がかかる場合は早期に税額を試算することが、相続放棄や納税資金準備の判断に不可欠です。
- 専門家への相談 相続は法律や税金が複雑に絡み合います。財産の評価、寄与分の主張、遺産分割協議、相続放棄や限定承認の手続き、相続税の申告・納税計画(延納・物納含む)など、少しでも不安や疑問があれば、早めに専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談しましょう。 特に、争いの兆候がある場合、借金が発覚した場合、納税資金に不安がある場合などは、期限や感情的なこじれが進む前に、専門家から的確なアドバイスを受けることが、適切な解決への近道となります。
まとめ:他人事ではない相続問題
「うちは大丈夫」と思っていても、いざ相続が発生すると、予想外の事態に巻き込まれる可能性は誰にでもあります。相続は、単なる財産の移転ではなく、家族関係そのものを見つめ直す機会にもなり得ます。
大切な家族との関係を壊さないためにも、そして、残された家族が困らないためにも、元気なうちから相続について考え、準備を進めておくことが重要です。「まだ先のこと」と思わず、一度立ち止まって、ご自身の家族の状況と照らし合わせてみてはいかがでしょうか。必要であれば、専門家の力を借りることもためらわないでください。
未来の安心のために、今できることを始めましょう。